※この記事は「B級家族ドキュメンタリー」の番外編です。
本編では、壊れた父と、転がる息子の生活を記録しています。
→ B級家族ドキュメンタリー:目次(一覧)はこちら
あの春、告白しなかった日
地元に帰って、父と姉と娘と暮らし始めた頃。
僕は企業向け給食弁当の会社で働いていた。
朝はまだ薄暗くて、空気が冷たい。
工場のシャッターがガラガラ開く音がして、湯気と醤油の匂いが鼻に入ってくる。
白いご飯の湯気って、なんであんなに「ちゃんと生きろ」って言ってくるんだろう。
職場には主婦の方や、定年後に短時間で働くおじさんが多かった。
若くて体力のある僕は、弁当配達で重宝された。
重宝されたっていうか、要するに「荷物持ち担当」だ。
重宝される理由が腕前じゃなくて筋肉って、男としてちょっと切ない。
配達を早く終えては、大変そうな人の手伝いに回っていた。
昼は時間との闘い。
12時までに終わらせないといけない。
信号のタイミング一つで世界が終わる。
弁当配達の世界は、わりと戦場だ。
配達員の中に、20代前半の女の子がいた。
頑張り屋で、少しドジで、でも気配りができる人。
配達コースが隣同士だったから、お弁当が足りなくなったり余ったりすると、会社用の携帯で連絡を取り合っていた。
そのうち業務連絡の中で、僕はおじさんダジャレを言って彼女を笑わせるようになった。
昼食後のひと休みには、コーヒーじゃんけんで盛り上がった。
勝ったら奢り。負けたら奢り。
つまり、勝っても負けてもコーヒーは飲む。
平和だ。こういう平和が、当時の僕には眩しかった。
「はい。オダギリジョーです」
そう言って電話に出ると、彼女は大笑いした。
僕の人生、これがピークでいいかもしれない。
オダギリジョーで笑ってくれる人、貴重。
でも家に帰ると、現実は別だった。
僕にだけ茶色いご飯が出されていた。
いつ炊いたのか分からない、あの匂い。
夜はただビールを飲んで過ごした。
テレビの音だけが部屋を埋めて、僕は何も言わずに飲んだ。
こういう話は、恋愛というより、生活の話になる。
もし本編から読んだ方がいい人は、ここからどうぞ。
→ B級家族ドキュメンタリー:目次(一覧)へ
10月に入社した僕は、年末年始の休み前に彼女を誘おうかと思った。
でもやめた。
まだ距離を感じていた。
それでも、「今日はこんな話をしたな」って思い返すたびに、少し距離が縮むだけで嬉しくなっていた。
そんな関係が続いて、季節は春になった。
道路沿いの桜が咲き始めて、風がやたら優しくなる。
配達中、窓を開けると草の匂いが入ってくる。
「ああ、春って、勝手に人の心をほどくよな」って思う。
ある日、いつもの雑談の中で、
「お花見行った?」
「行ってないよ。あたし、いちご狩りしてみたいな。あと牛の乳搾り!」
いちご狩りと乳搾り。
そのアンバランスが可笑しかった。
可愛いのか、たくましいのか、もう分からん。
家に帰ってネットで検索すると、奇跡的に両方体験できる施設があった。
高速で1時間半くらい。
誘わない理由はなかった。
誘うと、彼女はすごく喜んでくれた。
「お弁当作っていくね!」
その一言で、僕の心の中の何かが一気に春になった。
桜は葉桜になっていたけど、約束した。
LINEも交換した。
この日、僕は彼女に告白しようと決めていた。
言葉にすると簡単だけど、実際は胃がねじれる。
当日はドキドキだった。
行きの高速道路では、他愛のない会話をしながらドライブを楽しんだ。
窓の外は若い緑。
遠くの山が霞んで、空が高くて、車内だけが小さな世界みたいだった。
ラジオから流れる曲に合わせて、彼女が鼻歌を歌った。
それだけで、僕は「生き返る」感じがした。
乳搾りでは、牛が急に排泄するものだから、キャーキャー言いながら二人で逃げ回った。
牛は無表情で、こちらは必死。
人生ってこういうもんだ。
こっちは必死なのに、相手は無表情。
彼女の手作り弁当は、凄い量だった。
おにぎり、卵焼き、唐揚げ、ウインナー、彩り。
「これ運動部の遠足?」って量。
食べきれなかった。
早起きして料理する彼女の姿を想像して、僕は思った。
「絶対に彼女の心を掴みたい」
楽しい時間は、本当にすぐ終わる。
帰りの高速道路では、仕事中には見せない、少し甘えるようで、時々トゲのある言葉を彼女は言った。
そのトゲが、むしろ人間っぽくて、僕は嫌いじゃなかった。
「告白するなら今だ」
そう思った瞬間、彼女が真面目な口調で言った。
「相談があるんよ」
お客さんから告白されたこと。
その人がキャバクラ通いをしていること。
どうしたらいいか。
…このタイミングで、その話。
人生って、ほんと脚本家が意地悪。
もしかしたら、
「そんな人より僕と付き合おう」
その言葉を待っていたのかもしれない。
だけど、どうしてもその言葉が出なかった。
キャバクラ好きの、ちょっと困った男は、
心を入れ替えれば、
彼女を幸せにできるのかもしれない。
でも、僕は違う。
僕が彼女と付き合うということは、
彼女の人生に、
父と娘のいる生活を
そのまま差し出すことだった。
それで彼女が、
本当に笑えるのかどうか。
僕には、確信が持てなかった。
その後、何を話して帰ったのかは覚えていない。
ただ、別れ際に、
「もっと一緒にいたいな」
そう思ったことだけは覚えている。
彼女を見送って、コンビニでビールを2本買った。
夜風が少し冷たくて、道路の街灯がぼんやり白かった。
もうすっかり散ってしまった桜の木の下で、ビールを開けた。
花はないのに、枝だけが空に伸びていて、
なんだか僕みたいだった。
涙が出てきて、そのうち声を出して泣いた。
48分くらい泣いていたと思う。
U2の「ヨシュア・トゥリー」の最後の曲が流れていたから。
アルバム1枚が終わるまで泣いてたってことだ。
僕は、泣くにもロックの尺が必要な男だった。
――あの春、告白しなかった日。
ここまで読んでくれて、ありがとう。
このブログでは、派手に勝たない人の生活を記録しています。
本編の「B級家族ドキュメンタリー」は、こちらから読めます。
→ B級家族ドキュメンタリー:目次(一覧)
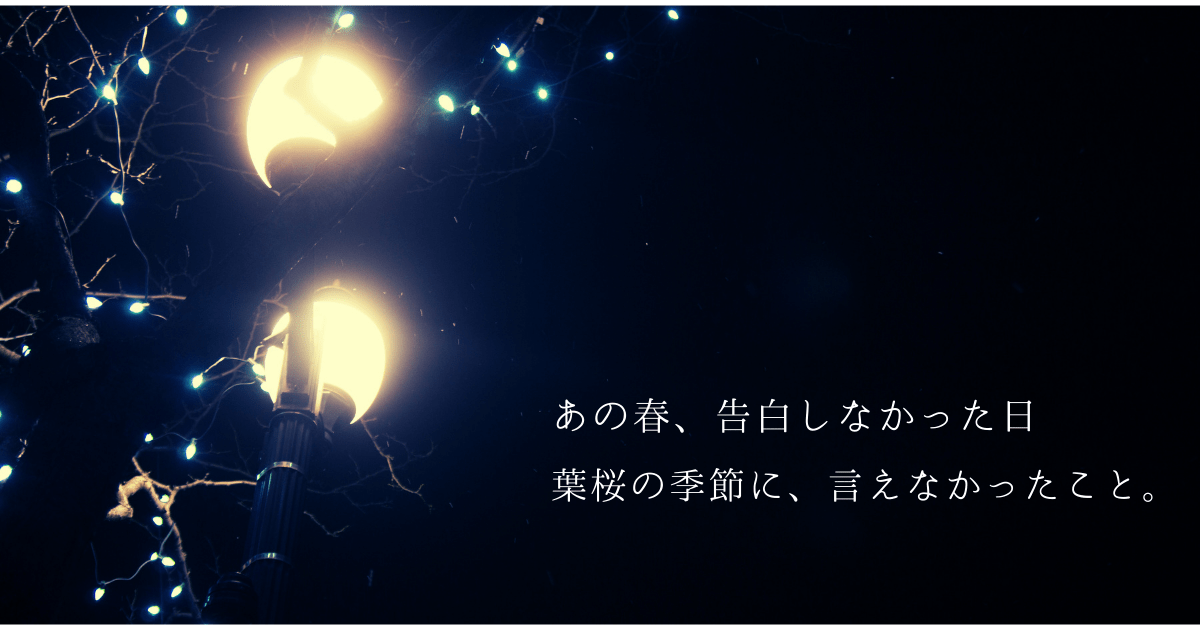







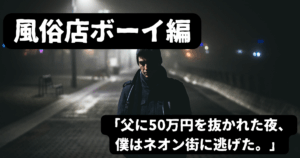
コメント