──ほどけていく祈り
娘の結婚式が終わってから、
父は半年に一回、姉と僕を食事に誘うようになった。
過去の話は、しない。
「今の仕事はどうなんか」
「体は元気なんか」
そんな当たり障りのない話だけをして、
最後に決まって、父は笑顔で封筒を差し出す。
中には一万円。
姉と僕に、それぞれ一万円ずつ。
今まで、そんなことは一度もなかった。
その一万円は、
「金でしか関われなかった父なりの距離感」みたいに見えた。
元妻の遺影を抱いて撮った写真
話を少しだけ結婚式の日に戻す。
式が終わったあと、
娘と僕は式場のすみっこで、
元妻の遺影を抱いて記念写真を撮った。
花嫁姿の娘の横で、
元妻は小さな額縁の中から、いつもの笑わない顔でこっちを見ていた。
カメラマンさんは、ちょっと困った顔をしながらも
「じゃあ、こちらに並んでくださーい」
と、ちゃんとシャッターを切ってくれた。
娘には「父と母と三人で食卓を囲んだ記憶」は一度もない。
それでも彼女は、
ちゃんと「家族のかたち」を自分なりに拾い集めて、
その日、その瞬間だけの家族写真を作ろうとしていたんだと思う。
あとから写真を見返して、
「この子にとって“家族”ってなんだったんだろうな」と、
何度も考えた。
そんなことを時々思い出しながら、
半年に一回の父との食事会に通っていた。
父は、以前の借金のせいで、
本家の後取りだった兄と縁を切られていた。
だから僕は、
先祖のお墓の場所も知らなかったし、
お墓参りに行く機会もなかった。
ある日、僕は父をお墓参りに誘った。
車で三十分ほどの道中、
父は、自分の兄弟の話、
亡くなった祖母の話、
武田家の由来なんかを、ぽつぽつと話してくれた。
それから僕は、
夏になると、ひとりでお墓参りに行くようになった。
まず、元妻が発見された場所へ行く。
「ごめんな」
何度も、何度も謝った。
それから、父方と母方のお墓を回る。
それでも、体調は安定せず、
僕は入退院を繰り返していた。
数年後、
父が目に見えて弱っていくのが分かるようになった。
食事をすると、
口からポロポロと食べ物がこぼれる。
自分でも気にしている様子だった。
話している言葉が、
聞き取れないことも増えた。
原因は、「歯茎にできた癌」だった。
それでも、
半年に一回の食事会は続いていた。
旅人みたいに眠り続けた一週間
2023年9月。
僕は入院していた。
入院して最初の一週間は、驚くほど眠かった。
ずっと眠っていた。
旅人が、ようやくくつろげる家に辿り着いたみたいに。
少し元気になると、
スマホを片手に病院を抜け出して、
こっそりタバコを吸いに行った。
見つかったら、強制退院だ。
そんなとき、姉からLINEが届いた。
「お父さんと病院に行ってきました。
もうすぐ入院します。
余命3ヶ月だそうです。」
不思議と、驚きはなかった。
「ついに、その時が来たか」
それくらい、父は目に見えて弱っていた。
父は入院してからも、
相変わらずお金の計算ばかりしていた。
一番近くに住んでいる姉が、
洗濯物などの世話をしていたが、
ある日、姉から連絡が来た。
「父から、
私がお金を取っているって言われた。
もう、父のところへは行かない。」
娘には、生後6ヶ月になる子どもがいた。
僕にとって、初孫だ。
頻繁に父のもとへ通うことは、
どうしてもできなかった。
結局、残ったのは僕ひとりだった。
休日のたびに、
車を走らせて、
60キロ離れた病院へ通った。
「父のやりたいことリスト」
11月。
看護師さんに呼ばれて、
一枚のメモを渡された。
父の「やりたいことリスト」だった。
父は歩行が困難になり、
車椅子生活になっていた。
酸素吸入も必要だった。
それでも、
ベッドに座って話はできたし、
ご飯もよく食べていた。
変わったことといえば、
食べ物をポロポロこぼすことを、
もう気にしなくなっていたことだった。
【父のやりたいこと】
・散髪
車椅子でも引き受けてくれる散髪屋を探し、
父を連れて行った。
散髪を終えて、
「鏡見てみなよ。サッパリしたよ」
そう言った瞬間、しまった、と思った。
そこに映っていたのは、
“サッパリした老人”じゃなくて、
「もうすぐ最終コーナーに入る父」の姿だったからだ。
・お正月は自宅で過ごしたい
1月2日。
父を自宅へ連れて帰った。
娘、娘婿、孫。
猫が2匹。
みんなで父を迎えた。
娘の手料理を食べながら、父は言った。
「ふぁけは、ほひたい」
聞き返すと、「酒が飲みたい」だった。
コンビニで酒を買い、
内緒で飲ませてあげた。
父は「美味しい」とは言わなかった。
でも、コップを持つ手は、
どこか誇らしげに見えた。
市内には、父の姉と妹が住んでいる。
留守かもしれないが行ってみようと提案すると、
父はニッコリ笑って、「いってみるか」と言った。
まず、父の姉の家。
90歳を越えていたが、まだまだ元気そうだった。
小学生以来の再会だ。
父は、車のそばまで来てくれた姉を、見もしなかった。
喋りもしなかった。
ただ、兵士が敬礼するみたいに、
左手を上げて別れた。
次は、父の妹の家。
そこでも、同じように、左手を上げて別れた。
帰り道、あの家の前を通った。
父の借金で手放した、あの家。
外観は変わっていなかったが、
表札だけは、知らない名前だった。
「おお!」
父は、歓声を上げた。
嬉しいのか、悔しいのか、
その声の中身までは、もう聞き分けられなかった。
病院への帰り道、父は何度も言った。
「けんひゃん、ふふほほほ」
聞き逃してはいけない気がして、
何度も聞き返した。
答えは、
「けんちゃん、福男」だった。
その一言だけで、
このどうしようもない親子関係が、
ギリギリのところで救われたような気がした。
【1月9日】
父の、もうひとつの願い。
初詣。
毎年行っていたらしい、小さな神社だった。
境内の近くに車を停め、
助手席のドアを開けると、
父は、幼い子どもみたいに、参拝を嫌がった。
外は、冷たい風が吹いていた。
仕方なく、僕ひとりで参拝し、
神社を後にした。
帰りに、コンビニへ寄った。
酒をやめた父は、すっかり甘党になっていた。
その日は、父も一緒に店内へ行きたいと言った。
車椅子は使わず、
自分の足で、ゆっくり、ゆっくり歩いた。
僕は、携帯用の酸素吸入器を引きながら、後ろをついて行った。
父は、ケーキの棚の前で立ち止まり、じっと動かなかった。
商品を選んでいるわけでもない。
ただただ、じっと動かなかった。
「このロールケーキ、おすすめよ」
そう言うと、ようやく動き出した。
車に戻ると、父はすぐにロールケーキを食べた。
相変わらず、ポロポロこぼしながら。
病院に着いて、
「次は21日に来るよ」
僕はそう言った。
本当は、その間にも休みはあった。
でも、体も、心も、限界だった。
父は、はっきりと「ありがとう」と言い、
右手を差し出した。
確かにはっきりと言った。
「ありがとう」
少し照れくさい気持ちで、握手をした。
それが、父との最後の別れだった。
約束の1月21日の翌日、
2024年1月22日
父は僕と姉の『お父さん』と、
僕の娘の『おじいちゃん』という役目を終えた。
葬儀のことは、すべて娘に伝えてあったらしい。
葬儀社も、お墓も、すべて手配されていた。
長男の僕は、生まれて初めての「喪主」を覚悟していた。
でも、喪主は娘だと、葬儀社の人から聞かされた。
また、重要な役目は、僕には回ってこなかった。
葬儀には、姉と母も現れた。
「亡くなったと聞いたら、
父への恨みがスッと消えた」
母は、そう言った。
母、娘、姉、僕。
4人だけの葬儀。
坊さんもいない。
4人で、父の骨を拾った。
「終わったなぁ」
そう思って外を見ると、
瀬戸内の街には、珍しいほどの吹雪が広がっていた。
雪は、みるみる積もっていく。
「今日のことは、
絶対に忘れられないだろうな」
そう独り言を言いながら、
僕は帰り道を急いだ。
遺影に選ばれた一枚の写真
葬儀の日、
娘が一枚の写真を見せてくれた。
「おじいちゃんから、
この写真を遺影にしてって渡されとったんよ」
そこに写っていたのは、
「○○公園へ行くの!」
父が地図を片手に僕を訪ねて来た日。
背景の風景を見れば、すぐに分かる。
いちばん父を嫌っていた頃の僕が、
絶対に見たくなかったはずの表情──
娘と並んで笑っている父の顔が、そこにあった。
娘には、
父と母と三人で食卓を囲んだ記憶はない。
父は父なりに、「自分と孫の写真」を
未来に残そうとしていたのかもしれない。
結婚式で
元妻の遺影を抱いて撮った写真。
葬儀で
父の遺影として祭壇に飾られた写真。
どちらも、
「ちゃんとした家族写真」ではないのかもしれない。
でも今の僕には、
そのどれもが、
このB級な家族にとっての
精一杯の “祈りのかたち” だったように思える。
【おわり】
書き終えたあと、
しばらく何も考えられませんでした。
たぶんそれで、いいんだと思います。
武田健治
エンディングテーマ「父を赦すことで、僕も少し赦された気持ちになりました。」
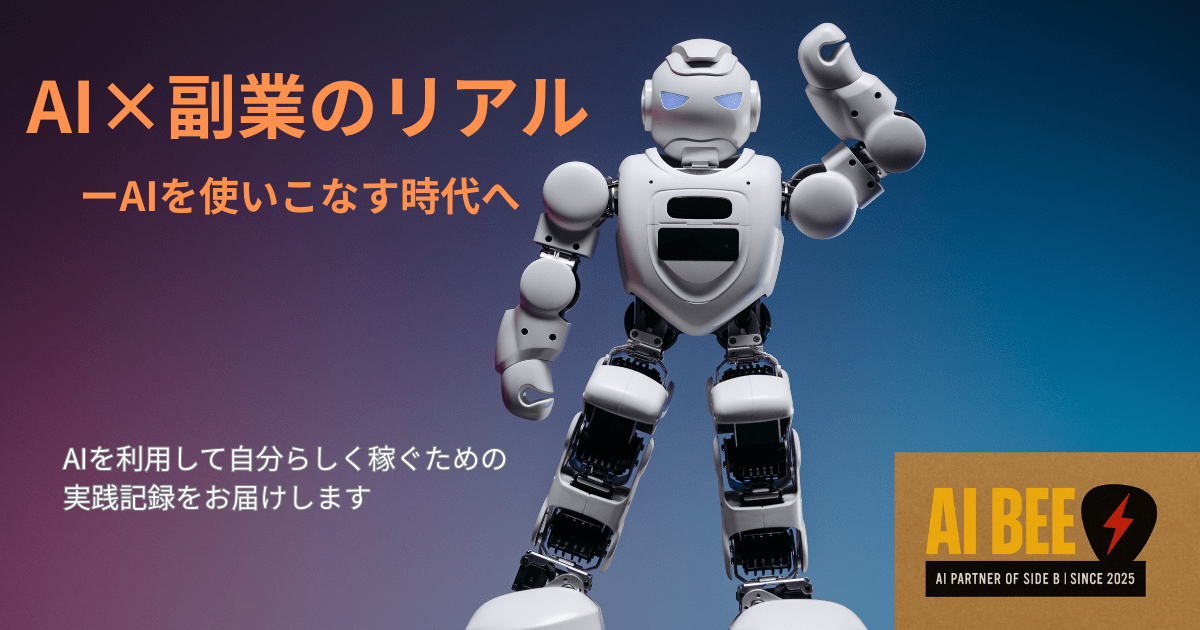
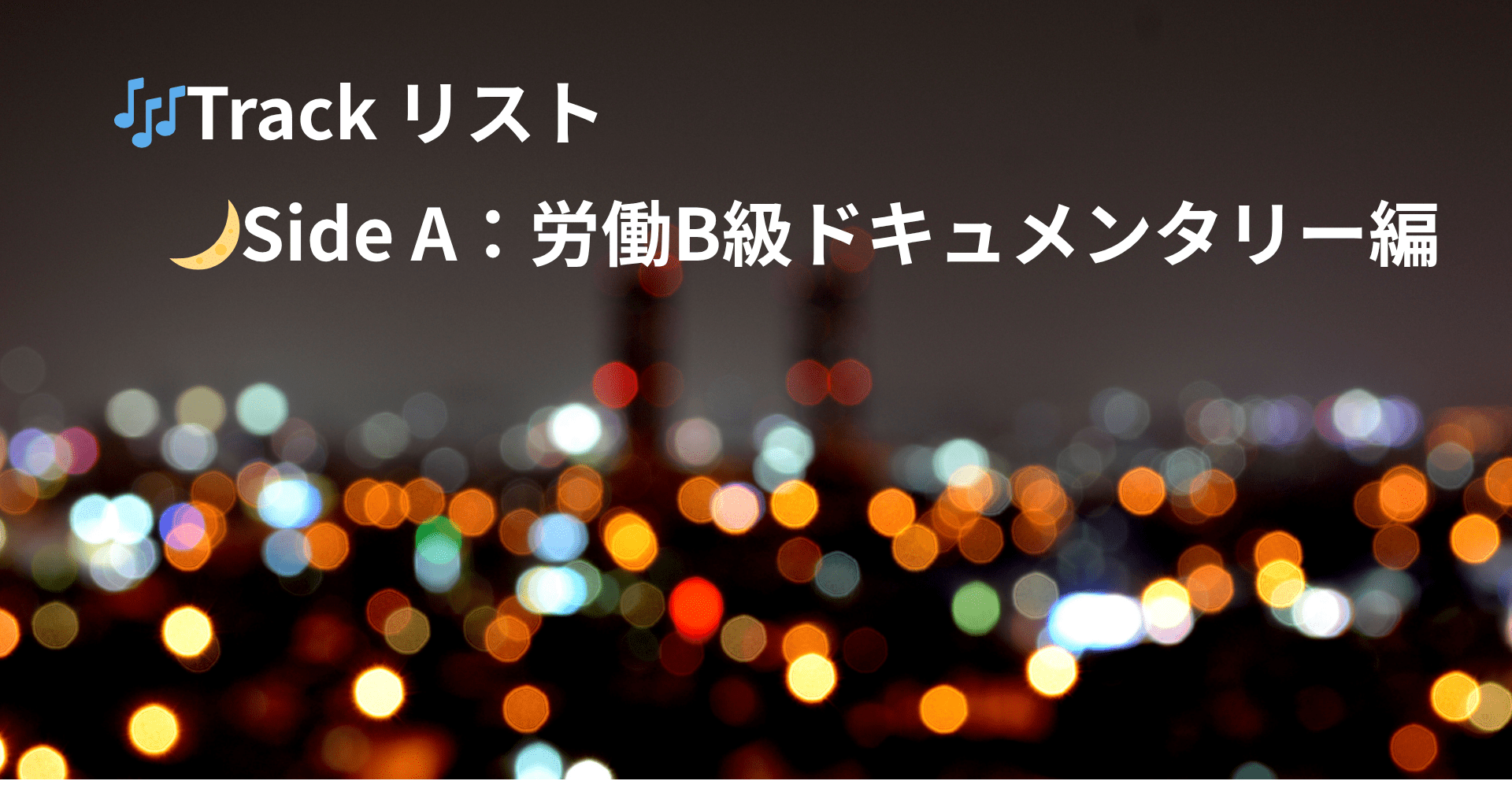




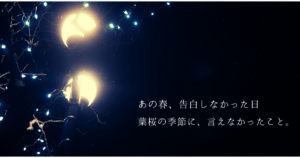
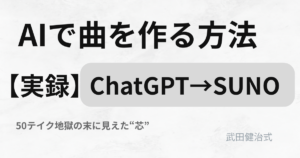





コメント