帰郷──娘と過ごした日々と、家の違和感
久しぶりに実家へ戻った。
娘は4年生になっていた。
久しぶりの再会なのに、
娘はあの頃と変わらない距離感で接してくれた。
ときどき僕の膝の上にぴょこんと座って、
一緒にパソコンでゲームをしたり、動画を見たり。
「父親ごっこ」みたいな時間が、思った以上にうれしかった。
家には、元妻の姿はなかった。
父の話では、
- 相変わらず新興宗教に出入りを繰り返し
- 精神病院へ入退院をくり返している
らしい。
その代わりに、家には 姉 がいた。
自慢だった姉の「その後」
姉は7つ上で、僕の自慢だった。
陸上競技の長距離選手として活躍し、
誰もが知っている実業団に所属していた。
テレビで何度も、姉の走る姿を観た。
地方の小さな家の居間に映る、
全国区の大会。
画面の中で先頭集団を走る姉を見ながら、
「うちの姉ちゃん、すごいじゃろ」
と、友達に自慢していた。
そんな姉が、実業団を引退して地元に戻り、
今は父と娘と一緒に暮らしている。
でも、本来なら姉が住むのは、
父と離婚した 母の家 のほうが自然な気がしていた。
ある日、母の家を娘と一緒に訪ねた。
母は、久しぶりに会う孫を本当にうれしそうに迎えた。
でも、娘はキョトンとしている。
「おばあちゃん」の記憶が、ほとんどない。
その光景を見て、胸がぎゅっと締めつけられた。
そこで、母から姉の話を聞いた。
姉は地元に戻ったあと、しばらくは一人暮らしをしていたらしい。
ある日、近隣の住人と騒音トラブルになり、
警察に連行された。
身元引受人になったのが、父だった。
そのまま姉は実家へ戻り、
父と暮らすようになった――という流れだった。
母は、ふと申し訳なさそうな顔をして、こう言った。
「お姉ちゃん、父さんから200万もせびられとったんよ。
母さんも、気づいてあげられんかった」
温厚で、いつもニコニコしていた姉。
テレビで走っていた、あの誇らしい姿。
どうしてそんなふうに追い込まれていったのか。
そのときの僕には、まだよく分からなかった。
「父親らしいこと」がしたかっただけなのに
一度だけ、娘の参観日に行った。
当時の僕は、まだ夜の仕事の風貌そのまま。
金髪にロン毛。
教室にいるだけで、どうしても居心地が悪かった。
先生が出す問題に、ほかの子どもたちは競って手を挙げる。
でも、娘は下を向いたまま、じっと座っていた。
「ちゃんと答えられんのが、恥ずかしいんかな」
「それとも、僕がいるから緊張しとるんかな」
いろんな想像が頭の中をぐるぐる回るけど、
結局その日は、何も聞けずに帰った。
ある日、娘が一生懸命電卓をたたいていた。
「なんしょん?」
僕が聞くと、娘はニコニコしながら答えた。
「算数の宿題!」
僕は大爆笑した。
「電卓使うんかい!」
でも、その瞬間、心のどこかで
「それでええ、それでええ」と思っている自分がいた。
- 完璧な答えを出すことより
- 楽しそうに問題と向き合っていることのほうが
- 何倍も大事に思えた
「父親らしいことがしたい」と思って帰ってきた僕にとって、
こういう小さな時間が、一番のごほうびだった。
同じ屋根の下で、じわじわと「自分だけ」が浮いていく
そんなささやかな幸せの裏側で、
家の空気は、少しずつおかしくなっていった。
ある日、父が僕の部屋に入ってきて、こう言った。
「お前が帰ってきてから、電気代が高うなった」
またか、と心の中でため息をつく。
それなりの金額は、毎月家に入れている。
昼の仕事に切り替えて、収入は夜より減ったけど、
「家族3人分の生活費」として、できる範囲で出していたつもりだった。
「また金の話か」
口には出さなかったけど、そう思った。
ある日の夕食。
その日は父が料理を作っていた。
大きなトンカツに、炊きたてのご飯。
娘は「おいしい!」と言いながら、嬉しそうに頬張っている。
ふと自分の茶碗を見ると、
なんとも言えない茶色の、ご飯が盛られていた。
いつ炊いたか分からないような匂い。
口に入れると、臭くて吐き出しそうになった。
「ああ、そういうことか」
言われなくても分かる。
「娘がおいしければ、それでいい」
そう自分に言い聞かせて、黙ってそのご飯を食べた。
数日後、とうとう僕の前には ご飯そのものが出てこなくなった。
娘たちは、美味しそうにご飯を食べている。
父は何も言わない。
僕の席だけが、ぽっかりと空いている。
「ああ、ここではもう、僕は“家族”以下なんだな」
そんな感覚だけが、静かに積もっていった。
姉の異変に、僕だけが気づいていた
その頃、僕だけが姉の異変に気づいていた。
- 仕事に行っていない
- 昼間から部屋にいる気配がある
- 物音がやけに多い
本来なら家にいないはずの時間に、
姉の部屋から、何度も何度も物音が聞こえる。
「あれ、仕事は?」
そう聞こうか迷って、結局何も言えずにいた。
ある休日、その家には僕と姉の二人だけだった。
僕は少し大きめの音で音楽を聴いていた。
といっても、壁ドンされるほどの爆音ではない。
ただ、いつもよりちょっとボリュームが高いかな、という程度。
いきなり、部屋の扉が開いた。
「うるさい!」
姉だった。
「ごめん、ごめん」
僕はあわててボリュームを下げた。
そのときの姉は、まだ「いつもの姉」の顔をしていた。
しばらくして、また部屋の扉が開いた。
今度の姉は、目つきが明らかに違っていた。
「お前が何しよるか、全部知っとるからな」
訳の分からないことを言いながら、
僕の服をぐいっと引っ張ってくる。
その手の力が、あまりにも強かった。
咄嗟に、手が出てしまった。
思い切り、グーで姉の左頬にパンチしてしまった。
自分でも「やってしまった」と分かるくらいの勢いだった。
姉は何も言わず、自分の部屋に戻っていった。
その直後、姉の部屋からものすごい音が聞こえ始めた。
- 何かが倒れる音
- 物が壁にぶつかる音
- ガラスが割れたような音
おそらく、自分の部屋をめちゃくちゃに荒らしていたのだと思う。
「ああ、もう普通の喧嘩じゃないな」
そう感じながらも、
僕にはどうすることもできなかった。
その瞬間、
「これは一線を越えたな」と、自分でも分かっていた。
「お前、ヤクザか」──家を出ることになった夜
その夜も、僕はひとり、
自分の部屋でコンビニ弁当を食べていた。
レンジで温めた弁当の匂いと、
どこか冷たい蛍光灯の明かり。
家に帰ってきているのに、
「帰ってきた感じ」はまったくなかった。
そこへ、ノックもなく父が部屋に入ってきた。
「おい」
短い一言。
顔を見た瞬間、「ああ、さっきのことか」と分かった。
「姉にあんなことしたら、姉は仕事に行けんじゃないか」
開口一番、それだった。
さっきの出来事――
姉が部屋に乗り込んできて、意味の分からないことを叫びながら胸ぐらをつかんできて。
咄嗟に手が出てしまって、思い切り殴ってしまったこと。
もちろん、殴った僕も悪い。
それは分かっている。
でも、あのときの姉の目も、言葉も、
明らかに「いつもの姉」じゃなかった。
それでも父の口から出てくるのは、姉のことだけだった。
「やられたけん、やり返しただけじゃ」
僕は、半分ふてくされたみたいに言い返した。
言い訳でもあり、本音でもあった。
父は、しばらく黙って僕の顔を見ていた。
そのあと、吐き捨てるように言った。
「……お前、ヤクザか。もう出ていけ」
「ヤクザか」
その一言が、やけに耳に残った。
夜の仕事をしていたこと。
金髪で、ロン毛で、
世間から見れば「まとも」じゃない生き方をしてきたこと。
父にとっては、その全部が一気に出てきた言葉だったのかもしれない。
言い返したいことは、山ほどあった。
- 姉の様子がおかしいのは前から気づいとったこと
- 仕事に行けてないらしい雰囲気
- 本当は、誰よりも姉のことを心配していたこと
でも、そのどれも口には出なかった。
父の「出ていけ」の一言で、
この家での僕の役目は終わったんだな、と
どこか冷めた頭で理解していた。
娘に別れも告げず、また家を出る
次の朝、まだ日が昇りきる前に起きた。
ガタガタと音を立てないように気をつけながら、
車に積めるだけの荷物を積んでいく。
服、パソコン、最低限の生活道具。
段ボールに詰めながら、
「また一からやり直しか」
と苦笑いする自分がいた。
ふと、廊下の向こうを見る。
娘の部屋のドアは閉まっている。
中で、いつも通り寝息を立てているはずだ。
――起こして、ちゃんと話すべきなんじゃないか。
「父さん、また出ていくけどな」
「お前のことは、ちゃんと想っとるけんな」
そう言って頭をなでてやるのが、
“父親らしい”やり方なのかもしれない。
でも、ドアノブに手をかけることはできなかった。
ここで顔を見てしまったら、
きっと家を出られなくなる。
ここで「またな」と言ってしまったら、
次にいつ会えるか分からない未来の重さに、耐えられなくなる。
結局、僕は娘の部屋の前を素通りした。
玄関のドアをそっと開ける。
外の空気は、少しだけ冷たかった。
エンジンをかける。
家の窓は、まだ眠ったままだ。
バックミラー越しに見える実家は、
どこからどう見ても「普通の家族の家」に見えた。
そこから、僕だけがはみ出していく。
アクセルを踏む足に力を入れながら、
心の中でひとつだけつぶやいた。
――ごめんな。
――いつか、ちゃんと迎えに来るけえ。
そう祈るように心の中で言い訳をして、
僕はまた、新しい街へ向かって走り出した。
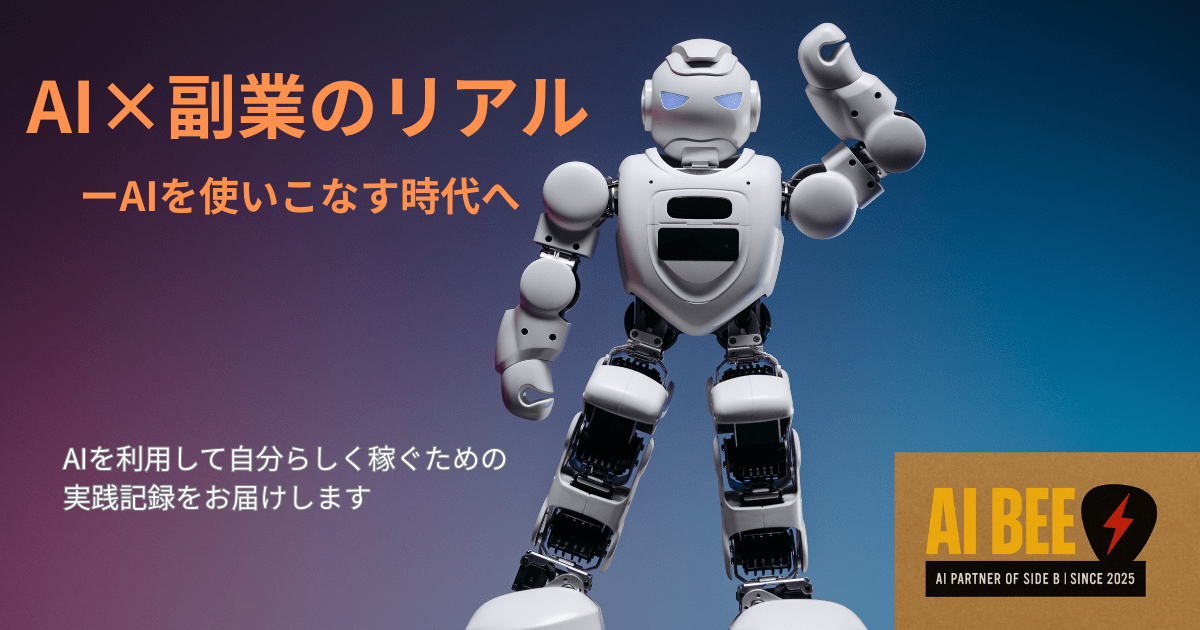
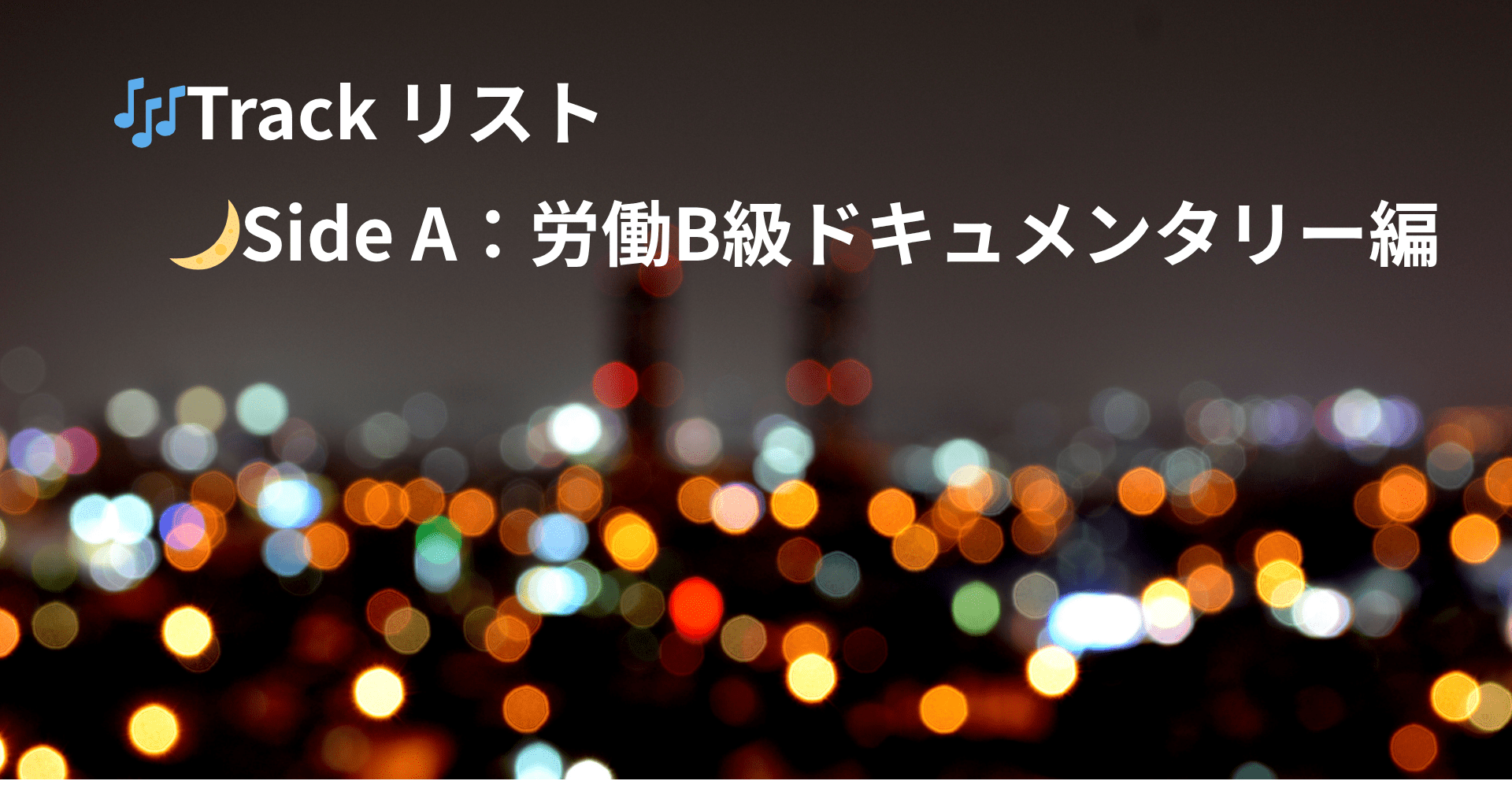





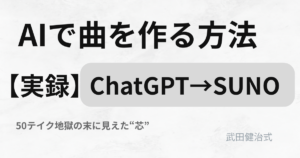

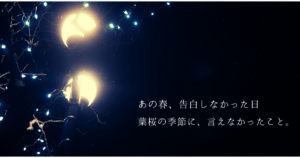



コメント