-家族がそろった最後の食卓ー
この記事のことを元に作成しました。BGMにどうぞ。
家を追い出されたあと、僕はまた夜の街に戻った。
「出戻り」というより、
人生という大河に流され続けていたら、
たまたままた風俗街の岸に打ち上げられました、くらいのノリだ。
夜の仕事が、嫌いだったわけじゃない。
酔っぱらいは面白いし、
同僚とのバカ話も嫌いじゃない。
ただそこに立っている「自分」だけは、
どうしても好きになれなかった。
それでも、他に行き場がない大人は、
だいたい夜の街に沈殿していく。
僕も、そのひとりだった。
姉に病名がついた日
しばらくして、姉が父を襲った。
ニュースだったら
「衝撃の一家トラブル」
みたいなテロップがつきそうな出来事だけど、
当事者としては、ただただ「マジかよ…」だった。
警察沙汰になって、病院に運ばれて、
そこで初めて“名前”がついた。
統合失調症。
その病名を聞いた瞬間の感覚は、
今でもうまく説明できない。
胸の中で何かがほどけたような、
逆に、全部のネジがいっぺんに吹き飛んだような。
あのときの、姉の意味不明なセリフ。
あの日の、獣みたいな目。
あの部屋から聞こえてきた、
何かを壊しまくる音。
あれ全部が、
「性格がキツいから」
「甘えてるから」
「努力が足りないから」
そういう雑なラベルじゃなくて、
病気の症状だった ということになる。
それが救いだったのか、
余計につらかったのか。
正直、いまだによく分からない。
気づいたら、十年ワープしていた
時間は、そこで一回途切れたみたいになって、
気づいたときには、いきなり十年くらいワープしていた。
気づけば僕はまた地元にいて、
地元の夜の街で働いていて、
いつの間にか、2回目の結婚もしていた。
ちゃんとやり直したつもりだった。
少なくとも、
「前よりはマシな人生」
を選んでいるつもりではいた。
そのうち、昼の仕事にも戻った。
夜から昼へ。
ちょっとまともな方向にギアを入れ替えたつもりだった。
ゴミ収集車の仕事をしながら、
でも、ある日を境に、
僕の中で何かが
ストン と音を立てて落ちた。
無断欠勤という、一番ダサい止まり方
朝、アラームは鳴る。
頭では「起きろ」と命令している。
でも、体が一ミリも動かない。
玄関に近づくと、
見えないバリケードにぶつかったみたいに足が止まる。
外に出ようとすると、
理由の分からない恐怖が喉元までせり上がってくる。
そのうち僕は、
家の内側からチェーンをかけるようになった。
「このチェーンが、外と俺を隔てている」
そんな、どうしようもない安心感に
すがるしかなかった。
髭も剃らないまま、
真夜中のコンビニへ酒を買いに行った。
この時点でも、まだ僕は
自分が病気だなんて、これっぽっちも思っていなかった。
ただただ、
「社会不適合のダメ人間」
だと思っていた。
両親が、説得に来た日
ある日、妻が
僕の父と母を連れて家に来た。
即席・家庭内三者面談だ。
3人とも、責める口調ではなかった。
怒鳴られることもなかった。
ただ、
「このままじゃダメだ」
「何とかせんといけん」
その空気だけが、
部屋の中を重く漂っていた。
「分かってくれているようで、分かっていない」
そんな感覚だった。
こっちは、
「分かってる。でも動けんから困っとるんよ」
と言いたいけど、言葉にならない。
どうにもならない空気だけを残して、
話し合いは終わった。
これが父との再会だった。
新しい仕事が決まり、
新しい家族は県外へ引っ越すことになった。
引っ越し当日、
七十を越えた父が、
よぼよぼしながらも手伝いに来た。
母は、弁当を持たせてくれた。
茶色いおかずと白いご飯。
いつもの、あの何でもない弁当なのに、
なぜか胸がぎゅっと詰まった。
父への恨みがないわけではなかった。
ただ、トラックを見送る父の年老いた姿をみて、
涙が少しだけこぼれた。
「全然ちゃんとできんかったな」
そんなセリフが喉まで出かかって、
結局、何も言えないまま、
車は新しい土地に向かった。
十年ぶりの娘と、「もう大人」の宣告
その少しあと、
父の配慮で、僕は娘と十年ぶりに会った。
十年。
小学生だった子が、
ガッツリ大きくなるには十分すぎる時間だ。
目の前にいた娘は、
もう大人の入り口に片足を突っ込んでいた。
「来年、結婚するんよ」
さらっと言うな、その爆弾を。
「お父さん、
ついこの前まで
お前の運動会のイメージで止まっとるんじゃが」
頭の中ではツッコみながら、
口から出たのは
「そうか〜」の一言だけだった。
時間は、ちゃんと娘を先に連れて行っていた。
置いてけぼりなのは、だいたい親のほうだ。
心の底から謝罪をした。
恥ずかしいくらい涙がこぼれた。
「お父さんのこと、恨んだじゃろう」
「寂しい想いをしたじゃろう」
娘は動揺したように、
黙って情けない父の姿を、ただただ見ていた。
タクシー、無理、崩壊、そして「うつ病」
新しい土地で、僕はタクシーの仕事を始めた。
知らない道。
知らない人。
知らない土地。
そこに
「時間に追われる」
というスパイスが乗る。
コロナも流行した。
メンタルに優しい要素、ゼロ。
今ならそう言えるけど、当時は
「家族のために頑張らないと」
モードがフル稼働していた。
無理した。
かなり無理した。
案の定、壊れた。
仕事ができなくなり、
初めて 入院 した。
そこでやっと、
病名が告げられた。
うつ病です。
「やっぱりな」と、
「マジかよ」が、同時にきた。
元妻が亡くなって、「自分で自分を有罪判決」
そのあと、元妻が亡くなった。
詳しいことは、
今でもちゃんとは書けない。
書こうとすると、
キーボードを打つ指が止まる。
「娘の結婚式を直前に控えてどうして?」
ただひとつだけ、はっきりしているのは、
あのときの僕は、
「自分が妻を殺した」
と本気で思っていた、ということだ。
自分のせいで追い詰めた。
自分がちゃんとしていれば。
あの時、新興宗教と本気で向き合っていれば。
「離婚はしていたけど、
心の中では“帰れば待ってくれている、
あの頃の家族”のままだった」
全部「自分が悪い」に回収して、
自分で自分に、有罪判決を出してしまっていた。
恨まれているに決まっている。
許されるはずがない。
命日が近づくたびに、
決まって調子を崩した。
「呪われている」
入院して、少し回復して、
「もう大丈夫かな」と思ったころに、また落ちる。
入退院を、くり返した。
今なら分かる。
それは罪悪感だけじゃなく、
病気の再燃 だったということ。
でも当時の僕には、
そんな冷静な区別はできなかった。
全部ひっくるめて、
「こんな自分は、生き延びてはいけない気がしていた」
バージンロードの「やっぱり」
娘の結婚式では、
僕がバージンロードを歩く予定だった。
「父親らしいこと、
やっと一個くらいできるかな」
そんな、ちっぽけな期待も
どこかにあった。
当日の控室で、娘がぽつりと言った。
「やっぱり、おじいちゃんと歩きたい」
一瞬、脳がフリーズした。
がっかりしたのか、
ほっとしたのか。
正直、自分でもよく分からなかった。
「そうか」
口から出たのは、それだけだった。
父は何も言わなかった。
少し背中を丸めながら、
娘の隣に立っていた。
似合っていた。
「ああ、こういうのは、
俺よりこの人の役目だな」
どこかで、
素直にそう思えた自分もいた。
三十年ぶりの「家族フルメンバー」
披露宴のあと、
父、母、姉、僕の4人が、
同じテーブルについた。
たぶん、三十年ぶりくらいの
家族フルメンバー集合 だ。
誰も仕切らない。
誰も「せっかくだから写真撮ろうや」と言わない。
昔話で大盛り上がり…するわけでもない。
ただ、
料理が静かに運ばれてきて、
それぞれが黙って箸を動かして、
ときどき誰かが小さく笑う。
それだけの時間だった。
不思議なことに、
居心地は悪くなかった。
あの家で感じていた、
空気が詰まる感じはなかった。
「家族らしい会話」は、
最後までなかった。
でも、それで十分だった。
あとから考えると、
あの食卓が、
家族全員がそろった最後の時間 だった。
そのときは、もちろん
そんなことは考えもしなかった。
人生は、だいじな場面ほど
「ここ大事だよー」と
テロップを出してくれない。
気づいたときには、
だいたいエンドロールが流れ始めている。
娘は、ちゃんと未来側に立っていた
娘は、きれいだった。
ドレス姿も、笑い方も、
ちゃんと「これからの人」の顔をしていた。
僕はといえば、
過去のあれこれを引きずったまま、
会場の隅っこで、
「よくここまで生き延びたな、おれ」
と、
ほとんど自分に向けてつぶやいていた。
時間は、勝手に前に進む。
人も、勝手に大人になっていく。
僕だけが取り残されている気もするし、
それでもまだ、
ここでこうして見届ける役だけは、
なんとか続けさせてもらっている。
この章は、
それに気づいてしまった男の、
ちょっと遅刻気味の報告書 みたいなものだ。
結婚式の日に、娘からもらった手紙
結婚式が終わって、
スーツのままソファに沈んでいた。
片付けの荷物の中に、
小さな封筒がまぎれていた。
表には、丸い字で僕の名前。
「お父さんへ」
……反則でしょ、そういうの。
震える指で封を開けて、
ゆっくりと便箋を広げた。
そこには、こう書いてあった。
「お父さんがいなくなったのは、
私が悪い子どもだったからだって、
ずっと思っていました。」
こっち側のセリフだと思っていた言葉が、
実は向こう側にもあった。
僕はずっと、
「父親失格の自分が全部悪い」
と思っていたけど、
あっちの世界ではあっちの世界で、
娘は、
「自分が悪い子どもだから、
いなくなったんだ」
と、自分を責め続けていたらしい。
手紙には、こうも書いてあった。
「久しぶりに会ったとき、
お父さんが泣いているのを見て、
ああ、私のせいじゃなかったんだって、
ちょっとだけホッとしました。」
さらに、追い打ちみたいに
こんな一文が続く。
「お母さんに寄り添えなかった自分を、
今でも責めてしまいます。」
そこで、やっと気づいた。
娘も娘で、
僕とは別の場所で、
「守れなかった側」 として
自分を責めていたんだ、ということに。
いなくなった父親を責める自分。
支えきれなかった母親を責める自分。
何もできなかった自分を責める自分。
その全部を、
一枚の便箋にぎゅっと押し込めて、
最後にこう書いてくれていた。
「それでもお父さんに、
ちゃんと『ありがとう』と言える大人になれて
よかったです。」
便箋をたたむ手が、
うまく動かなかった。
「父親をやれなかった自分」
「娘を置いてきた自分」
「妻を救えなかった自分」
それがいっぺんに押し寄せてきて、
ソファの上で、
当時40代のおっさんは、
声を出さないように泣いた。
……たぶんこの日が、
「父親として失格だった自分を、
それでも父親だと呼んでもいいのかもしれない」
と、
初めて思えた日だったのかもしれない。

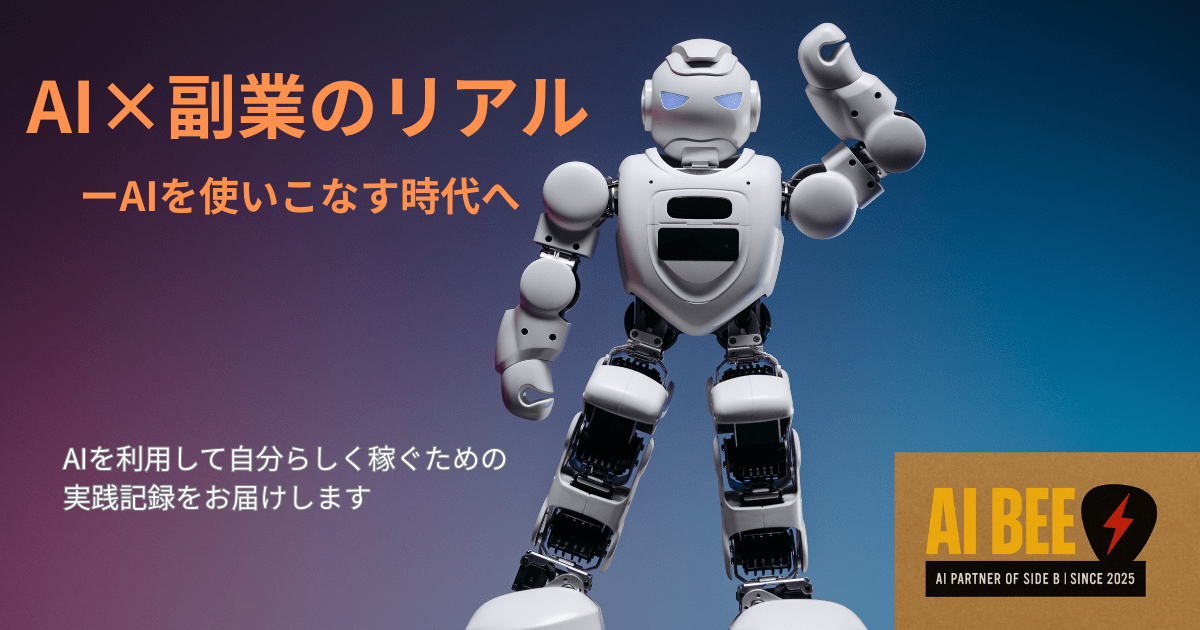
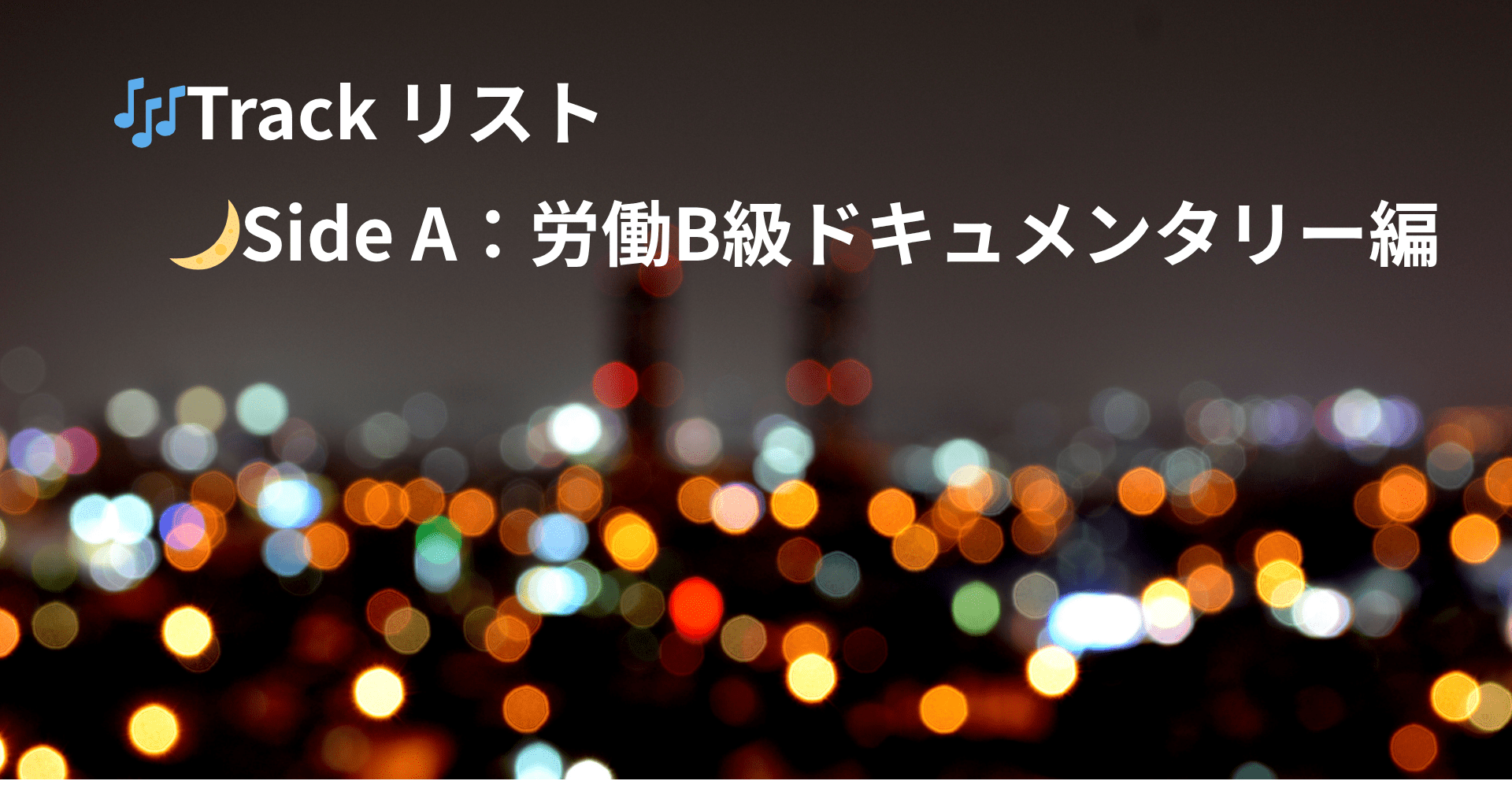


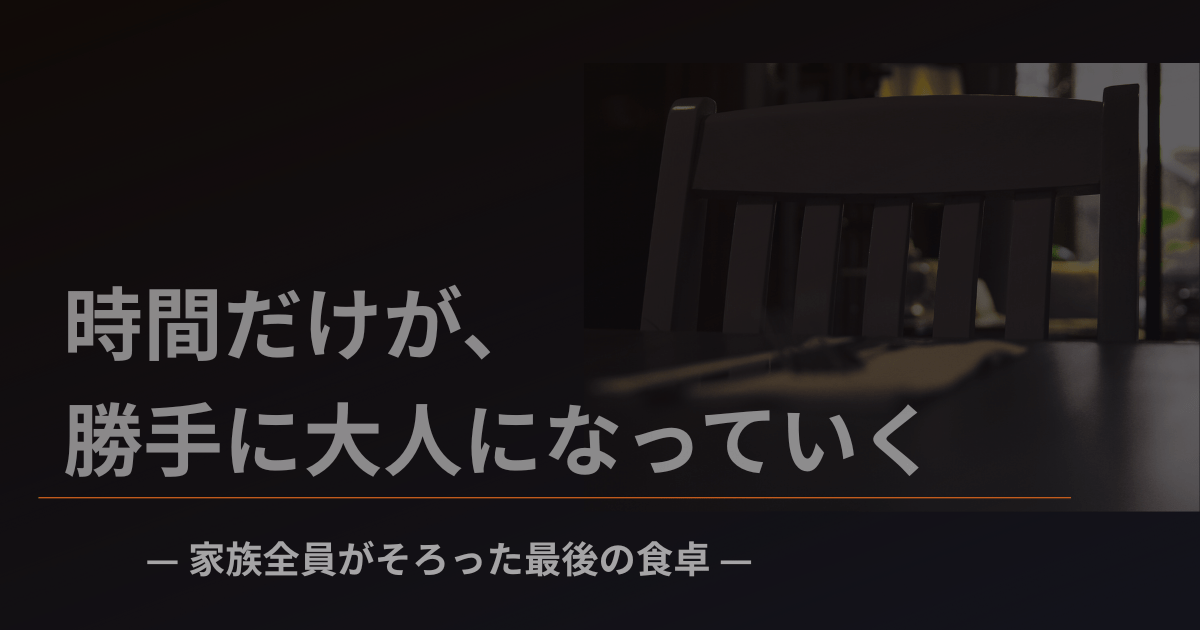


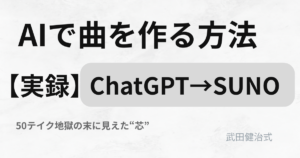

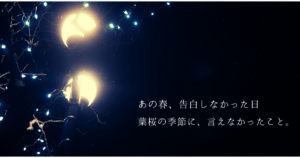



コメント