父との再会──風俗店の玄関前で地図を持つ男
※これは、父親として「月3万円」を背負うことになった、
ある日の話です。
店をクビになった僕は、知人を頼って新しい街の、新しい店で勤務を始めた。
今は法律がかなり厳しくなっているけれど、当時はまだ、
風俗店の玄関前に立って客引き行為をするのが「普通」の時代だった。
今でも、「あなたのいちばん得意な仕事は何ですか?」と聞かれたら、
間違いなくこう答えるだろう。
「客引きです」
長年客引きをしていると、
店に向かって歩いてくる人の 歩き方・目線・服装 を見るだけで、
その人が店に入るかどうか、だいたい予測できるようになる。
・ここを通り過ぎるだけの人
・他店を探している人
・こっちを見ないようにしながら、でもちょっと期待している人
タクシー運転手が、歩道を歩く人を見ただけで
「あ、この人はタクシーを探してるな」と分かるように、
こっちにも、こっちなりの“匂いで分かる勘”があった。
その日も、いつものように店の玄関前に立っていた。
昼間の、少し気だるい時間帯。
ふと視界の端に、ひとりの男性が入ってきた。
手には紙の地図。
スマホのナビなんてまだない時代だ。
どこかを探しているのか、ゆっくり周りを見回しながら歩いてくる。
いつもの僕なら、迷わず声をかけている。
「どちらかお探しですか?」
そこから世間話をつなげて、
うまくいけばそのまま店に案内する。
小さな親切が、そのまま見込み客に変わる。
それが、僕の客引きスタイルだった。
でも、その時は違った。
僕は反射的に、玄関のドアを開けて店内に逃げ込んだ。
しばらくして、店長に呼ばれた。
「おい、ちょっと来てくれる?」
バックヤードに入ると店長が、
なんとも言えない顔でこっちを見た。
「……お父さんから電話があった。今、近くの百貨店に奥さんと娘さんも来とるって」
あの紙の地図の男。
やっぱり父だった。
百貨店には、元妻と娘がいるらしい。
「時間は気にするな。顔だけでも見て来い」と店長は優しく笑った。
娘と会うのは、3年ぶりだった。
言われるままに百貨店まで行くと、
エスカレーター脇のベンチで、父と元妻と娘が並んでいた。
娘は、あの頃より少し背が伸びていて、
でも笑い方はまったく変わっていなかった。
「これからおじいちゃんと○○公園に行くの!」
このあたりでは定番の観光スポットの名前を、
得意げに僕に教えてくる。
事情を知っているのは、大人だけ。
元妻は少し離れたところで、ただ静かに笑っていた。
・今どこに住んどん?
・体は大丈夫なんか?
・仕事はキツいじゃろう
相変わらず、肝心なことはあまり聞いてこない人だったけど、
それでも「気にはしてたんだな」と分かる程度には、
父なりに心配してくれていた。
電話番号が変わっていたので、そこで改めて番号交換をした。
その日はそれで解散。
「また連絡するわ」
短い時間だったけど、家族との再会だった。
娘の無邪気な笑顔が、少しだけ僕の心を軽くしてくれた。
後日、父から電話がかかってきた。
「おう、元気にしょんか」
いつもの世間話のあと、唐突に本題が降ってくる。
「でな、養育費の話なんじゃけど」
要約すると、こうだ。
・娘のために
・月々3万円でいいから
・ちゃんと払ってやれんか
風俗街まで息子を探しに来た理由。
それは感動的な親子の再会でも、
涙ながらの和解でもなく、わりと実務的な「養育費の回収」 だった。
電話を切ったあと、
僕はしばらく天井を見つめながら笑ってしまった。
「ああ、うちの親子関係って、やっぱりこういう距離感なんだな」
感動の再会ドラマにはならない。
でも、「金だけの関係」ってほど冷たくもない。
地図を片手に歩いてきた理由は、娘との再会でも、息子の顔を見に来たわけでもなく、
きっちり「お金の話」だった、というオチ付きである。
それでも、電話を切ったあと、心のどこかで少しだけホッとしている自分がいた。
――ああ、自分はまだ、「父」として何かをさせてもらえる余地があるんだな。
父へのモヤモヤと、娘への申し訳なさと、
それでも月3万円という数字にしがみつこうとする、自分の小さなプライドと。
あのときの僕は、その全部をまとめて抱えたまま、
夜の街にまた出ていくしかなかった。
当時の僕は、
「払えるかどうか」よりも、
「父親でいられるかどうか」のほうが、正直よく分かっていなかった。
ただこのときは、まだ知らなかった。
――この「月3万円の父親業」が、あとで僕の人生にもう一回、大きく入り込んでくることを。
それから、あっという間に時間が過ぎた。
気づけば「養育費を払う父親」であることだけが、生活の芯に残っていた。
しばらくして、なぜか僕は店長に抜擢された。
人手不足の業界あるあるで、「真面目にサボらず来てるやつ」が、そのまま役職につくパターンである。
・女の子のシフト管理
・売上の管理
・クレーム対応
・オーナーからの理不尽な無茶ぶり
客引き一本でやっていた頃とは比べものにならないプレッシャーが、毎日じわじわ肩に乗ってきた。
それでも、毎月3万円だけは欠かさなかった。
給料日になると、銀行のATMで、淡々と送金する。
「父親らしいことなんて、何ひとつできてないけど、これだけは続けよう」
ほとんど意地みたいなものだった。
気がつけば、33歳になっていた。
店長としての責任とストレスは、そのまま生活の荒れ方に直結する。
寝る時間は不規則になり、コンビニ飯で胃を誤魔化し、酒の量だけがきれいに右肩上がり。
「休みの日にちゃんと休む」という発想は、いつの間にかどこかへ消えていた。
そんなある日、珍しく店に一本の電話が入る。
「おう、わしじゃ。今、そっちの街に来とるんじゃけどの」
父だった。
その日は、ひとりで店を訪ねてきた。
前みたいに元妻や娘はいない。昼間の営業前、まだ看板も灯っていない時間帯。
バックヤードの椅子に座って、父はペットボトルのお茶をちびちび飲みながら、ぽつりと言った。
「……そろそろ帰ってこんか?」
説得じゃない。
期待でもない。
ただ「戻れる場所がまだある」と差し出された気がした。
説教でもなく、涙の説得でもなく、ほんとうに一行だけ。
それでも、その言葉を聞いた瞬間、頭の中に浮かんだのは娘の顔だった。
百貨店のベンチで、「これからおじいちゃんと○○公園に行くの」と笑っていたあの顔。
毎月3万円の向こう側にいる、小さくて、でも確かに存在している「誰か」のこと。
――もう一回、昼の世界に戻ってみてもいいかもしれない。
そう思ったときには、心の中ではほとんど答えは出ていた。
僕は店を辞めて、地元に帰ることを決めた。
夜のネオンに守られていた生活をいったん終わらせて、
もう一度、昼の仕事でやり直してみようと腹をくくった。
振り返ると、
あれは人生を立て直す話じゃなく、
人として踏みとどまっただけの話だった。
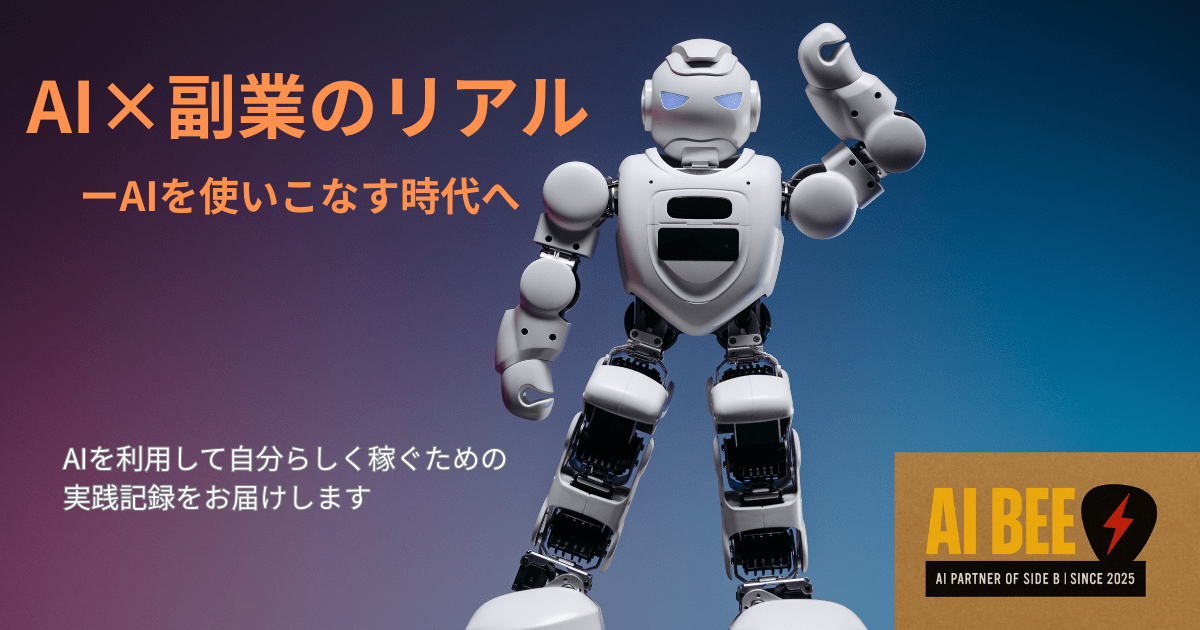
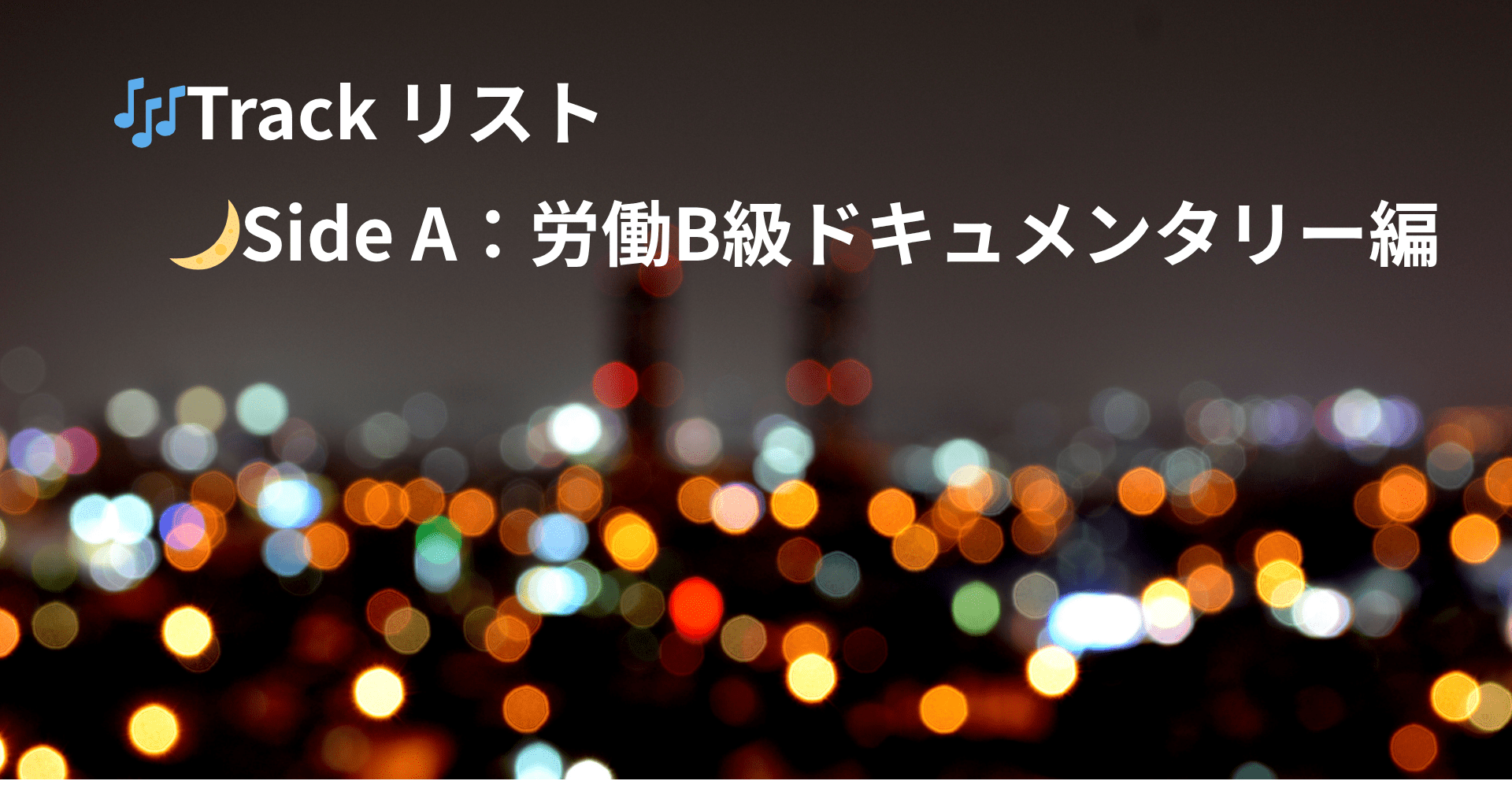





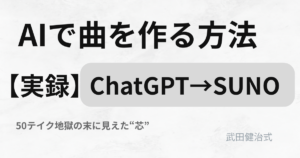

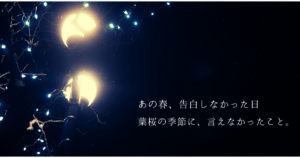



コメント