ー風俗店員の禁断の社内恋愛編ー
「社内恋愛は重罪」──それが夜の店のルールだった。
それでも僕は、彼女にCDを渡し、電話番号を書いたメモを忍ばせた。
あの日から、止められない恋と、止めきれなかった選択が始まった。
この記事のBGMはこの曲がオススメです。
出会い: “仕事だから”のはずだった
夜の店で、いちばん重い罪は何か知ってるだろうか。
パワハラをすることでも、
顧客情報を流出させることでもない。
社内恋愛だ。
店はキャストが体を張って働くことで成り立っている。
とくに人気キャストには、替えがきかない。
男性スタッフなんて、いくらでも代わりがいる。
だから社内恋愛が発覚したら、罰金50万円、降格、県外の系列店へ強制異動。
僕が働いていた店では、それが当たり前だった。
それでも、僕は彼女に惹かれていった。
境界線が溶ける夜
彼女は、どこにでもいそうな“普通の女の子”だった。
派手なネイルでもなければ、ぶっ飛んだトーク力があるわけでもない。
でも休憩室では、いつもニコニコ笑っていた。
「ねえ、またあれやってよ。『北の国から』のお父さんのやつ」
ドリンクを片手に、子どもみたいな顔でせがんでくる。
お笑い番組が大好きで、芸人のネタだけじゃなくて、
古いドラマのセリフまでよく覚えていた。
僕が田中邦衛の声マネで
「じゅ〜ん、ほた〜る……」
とやると、テーブルをバンバン叩きながら笑う。
その笑い声を聞いているだけで、こっちまでおかしくなってくる。
気づいたら、僕はその空気ごと、好きになっていた。
でも、この世界では社内恋愛は重罪だ。
好きになった時点でアウト。
そう分かっているからこそ、気持ちにフタをして、スタッフとしての距離を守ろうとしていた。
きっかけになったのは、ある夜の何気ない会話だった。
「ねえ、この前の送迎のときに流れとった曲、あれ○○(アーティスト)の?」
「○○(好きなアーティスト)の新曲よ。昔から好きなんよ」
「え、一緒じゃん。あたしもずっと聴いてる」
ロッカー前で、そんな他愛もない話になった。
仕事の愚痴でも客の話でもなく、好きなアーティストの話で盛り上がることなんて、それまで一度もなかった。
「今度CD貸してあげるよ。」
そう言うと、彼女は目を丸くして笑った。
そのやり取りのあと、僕は本当にCDを一枚、家から持ってきた。
店に私物のCDを持ち込むのは、本当はダメだ。
見つかったら、店長に呼び出されて小言を食らうのは分かっていた。
それでも、その夜だけは、もう一歩だけ踏み込んでみたかった。
家でケースを開けて、中の歌詞カードのあいだに、小さく折りたたんだ紙をはさんだ。
そこに、自分の携帯番号を書いた。「もし良かったら電話ください」
彼女がもし誰かに「これ借りたんよ」と見せれば、
店長に呼ばれて怒られるかもしれない。
「スタッフとキャストが連絡先交換なんかするな」と叱られる光景が、頭にはっきり浮かんでいた。
それでも、そのリスクごと抱えたまま、CDを持っていくことにした。
「ほら、この前言っとったやつ。」
バックヤードでそっと手渡すと、彼女は笑って受け取った。
「ありがと。大事に聴く。」
その笑い方が、いつもの「北の国から」に爆笑している顔とは、少しだけ違って見えた。
それが、線を越えた最初の一歩だった。
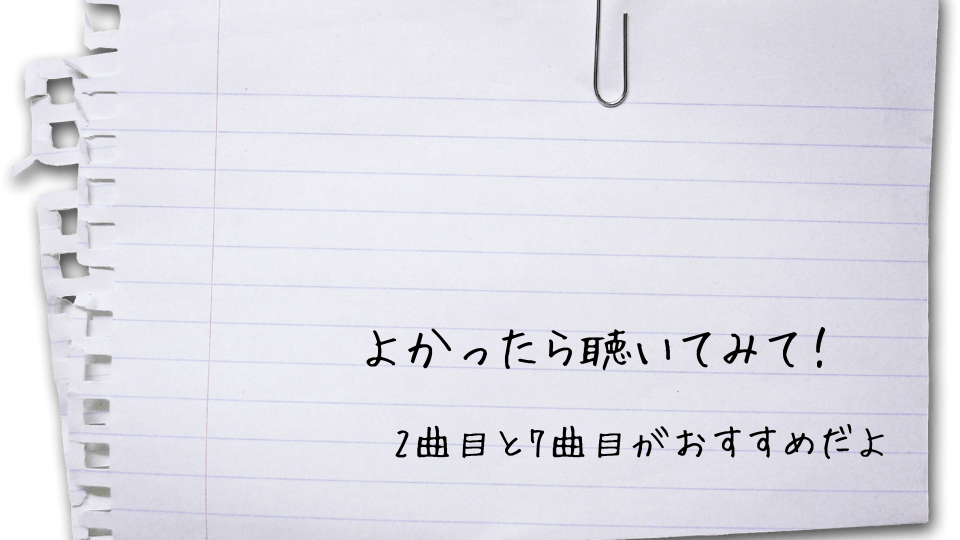
その数日後、閉店後に男性スタッフだけで焼き肉屋に行くことになった。
深夜までやっている、店から少し離れた、いつもの店だ。
「おつかれー!」
「今日もよう動いたなぁ」
カルビとビールで、みんなのテンションはすぐに上がっていく。
仕事中には言えない愚痴も、ここでは遠慮なく飛び交う。
そんなときだった。
テーブルの上に置いていた僕の携帯が、ぶるぶるっと震えた。
見たことのない番号だった。
「誰ね、こんな時間に」
誰かがそう言って笑った。
胸の奥が、少しだけざわついた。
CDを渡した日のことが、頭の中によみがえる。
「ちょっとトイレ行ってくるわ。腹いてぇ」
わざと少し大げさにお腹を押さえて、席を立った。
みんなは「またかい」と笑いながら、肉をひっくり返している。
店の一番奥にある個室トイレに入って、ドアを閉める。
ファンッと換気扇の音が鳴った。
深呼吸をひとつしてから、着信履歴を開き、さっきの番号にかけ直した。
ワンコール、ツーコール。
「……もしもし」
小さな声だった。
でも、すぐに分かった。
彼女だった。
「電話しちゃった・・・」
便座に腰を下ろすふりをしながら、僕は天井を見上げた。
「今男性スタッフで焼肉たべてるんよ。」
「いいなぁ。あたしも食べたい」
電話の向こうで、彼女がふっと笑う。
その笑い方が、さっきまで焼き肉屋のテーブルで聞いていた男たちの笑い声とは、まるで違う音に聞こえた。
「電話くれてありがとう。嬉しいよ。」
そう言うと、受話器の向こうで、少しだけ間があいた。
「……じゃあ、この後もうちょっとだけ付き合って」
その一言で、僕は完全に戻れなくなった。
焼肉店を出た後、すぐに電話をかけなおした。
店では見せない”素の彼女”がそこにいた。
その夜から、僕と彼女は「客とキャスト」でも「スタッフとキャスト」でもない、
もうひとつ別の関係になっていった。
誰にも言えない関係
それからは、自然と彼女が僕の部屋に来るようになった。
シフトが早く終わった日や、連休の前の夜。
コンビニの袋をぶら下げて、
「カップラーメン買ってきたけぇ、お湯沸かして」
と、当たり前みたいな顔で上がり込んでくる。
ふたりで缶ビールを開けて、小さな乾杯をする。
しょうもないバラエティを見ながら、
「こいつら絶対裏で仲悪いよな」とか言って笑う。
それだけで十分だった。
付き合おう、とか、彼氏彼女になろう、とか、
そんな言葉をわざわざ確認しなくてもいい気がしていた。
しばらくして、彼女は一週間ほど故郷の沖縄に帰ることになった。
「ちょっと実家戻ってくるわ。親にも顔見せんと怒られるけぇ」
そう言って、いつもより少し大きめのキャリーバッグを引きずって店を上がった。
僕は「お土産、ちんすこうでええから」と、冗談半分で手を振った。
”彼女の家族”と”僕の家族”
異変に気づいたのは、その里帰りから戻ってきてからだ。
ふたりで部屋にいても、彼女はどこか上の空だった。
テレビを見ていても、笑うタイミングがずれている。
コンビニ袋をテーブルに置いたまま、ぼーっと台所のほうを見つめていることが増えた。
「どうしたん? なんかあった?」
と聞いても、
「別に。なんもないよ」
とだけ言って、すぐ話をそらす。
ソファに座るその後ろ姿が、いつもより小さく見えた。
思わず、後ろからそっと抱きしめた。
「……大丈夫じゃけぇ」
と言おうとした瞬間、彼女は僕の腕をパッと払いのけた。
「ごめん、今そういう気分じゃない」
あのときの拒否は、ただの「今日はそんな気にならん」という話じゃないと、
どこかで分かっていた。
何かが変わり始めている。
でも、まだその名前が分からなかった。
「うちの妹さ、大学行きたいんよ」
「ふーん。ええじゃん。行かせちゃりゃええが」
軽く返したつもりだった。
でも、彼女は笑わなかった。
「行かせてあげたいの」
缶をぎゅっと握りしめたまま、テーブルを見つめている。
「でも、うちにはそんなお金がないの。
だから、あたしがソープで働く。」
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥がザワっとした。
僕の父の顔が、勝手に頭に浮かんだ。
新聞奨学生で、朝刊配って、そのまま学校行って、
授業中に何度も机に突っ伏して寝ていた頃の、自分の姿もいっしょによみがえる。
「けん、大学進学は諦めてくれ。」
”僕の家は他とは違うんだ”あの劣等感に苛まれた日々。
もし妹さんが、あの頃の自分と同じ道を歩くのだとしたら――
そう思うと、彼女がそこまでしようとしている理由が、少しだけ分かる気がした。
それでも、本音を言えば分からなかった。
どうして、そこまで自分を削る必要があるのか。
一度だけ、妹さんに会ったことがある。
沖縄から彼女を訪ねてやってきたとき、
ふたりでボロ車に乗って、空港まで迎えに行った。
到着ロビーで、妹さんを見つけた瞬間の彼女の顔は、
僕が見たことのない表情だった。
「あー! 来たー! 遅いし!」
そう言いながら、子どもみたいに走っていって、思いきり抱きついた。
その横で、僕は少し離れて荷物を持ちながら、
“家族”というものを遠くから眺めている他人、みたいな気分になっていた。
車の中でも、彼女はずっと笑っていた。
僕に見せるのとは全然ちがう、油断しきった笑い方だった。
バックミラー越しに、後部座席でじゃれ合う姉妹を見ながら、
「この笑顔を守るためなら、あの子は本当に何でもするんじゃろうな」
と、ふと思った。
その「何でも」の中に、自分が入っていないことくらい、分かっていた。

「ソープに行く」覚悟と、止めようとした僕
それをはっきり突きつけられたのは、ある夜だった。
仕事終わりに部屋でダラダラしていると、ドアがドンドン叩かれた。
「おーい、開けて〜……寒い〜……」
ドアを開けると、そこにはベロベロに酔っぱらった彼女が立っていた。
コンビニの袋はぐしゃぐしゃ、足元はふらふら。
部屋に入った途端、靴も脱ぎきらんうちに、そのまま畳に倒れ込んだ。
「おいおい、大丈夫か。どこまで飲んだんや」
返事の代わりに、「うぇっ」と嫌な音がした。
次の瞬間、敷きっぱなしの布団の上に、思いきりゲロった。
「ちょ、ちょっと待て! そこだけは勘弁してくれ!」
慌ててティッシュとバスタオルを持ってきて、
彼女の背中をさすりながら、心の中でため息をついた。
しばらくして、彼女の呼吸が少し落ち着いてきた。
横向きに寝かせて、水を飲ませると、天井を見たままぽつりと言った。
「……面接行ってきた」
「は? 何の?」
「ソープ。来月1日から働く」
彼女の決心は本物だったのだ。
自分の葛藤と闘って、今こうして泥酔している。
「本気よ。今日、店見てきた。
条件も聞いた。来月から入れるって」
そこで、やっと自分の中の何かが切り替わった。
「──やめろ」
自分でも驚くくらい、低い声が出た。
「妹さん、大学行くのにいくらいるん?」
「だいたい50万くらい」
「じゃあ、その50万、俺が出す」
気づいたら、口が勝手にそう言っていた。
「知り合いの店で移籍金貸してくれるとこあるけぇ、
そこから借りて、俺が払う。一緒にその店に行こう。」
酔いも一気に冷めていた。
頭の中では、全然現実的じゃない計算を必死に回していた。
彼女は、しばらく天井を見つめたまま黙っていた。
やがて、ゆっくりと首を横に振った。
「……ありがとう。でも、違うんよ」
「何が違うんや」
「妹を大学に行かせてあげたいのは、
“誰かに出してもらったお金”じゃなくて、
“あたしが稼いだお金”で行かせたいけぇなんよ」
「俺のお金でも、あんたのお金でも、
妹さんから見たら一緒じゃろが」
そう言いかけて、やめた。
彼女はゆっくりとこっちを見た。
「お父さんみたいな人に、これ以上振り回されたくないんよ。
“出してやった”“育ててやった”って言われるの、
もう終わりにしたいんよ」
その「お父さん」という言葉に、僕の父の顔も重なった。
「だから、自分で稼ぐ。
あたしがソープで稼いだお金で、妹を大学に行かせたいんよ」
そこまで言われてしまうと、もう何も返せなかった。
止めたかった。
本気で止めたかった。
でも、「やめろ」と言うことは、
彼女の覚悟ごとへし折ることになる気がして、
その言葉がどうしても喉を通らなかった。
気づいたら、僕は彼女を抱きよせていた。
沖縄から帰ってきて以来、ずっと触れないようにしていた身体に、
もう一度、しがみついた。
他の誰かの男になってほしくなかった。
まして、見知らぬ客のものになってほしくなかった。
その夜だけは、現実もルールも見えないふりをして、
ただ彼女の体温だけを確かめるみたいにして、一晩をやり過ごした。
翌朝、カーテンの隙間から差し込む光の中で、
僕は心のどこかで分かっていた。
昨夜どれだけ抱きしめても、
彼女の決意は、もう変わらないだろうということを。
2月1日の暴発
そして、2月1日が来た。
その日は、彼女がソープで働き始める日だった。
出勤はした。
タイムカードも押した。
でも、仕事にならなかった。
指示を聞いても頭に入ってこない。
客の顔なんて、まったく覚えられない。
同僚に何か言われても、上の空で「うん」としか返せない。
「体調悪いんなら、今日はもう上がれ」
そう言われて、僕は素直にそれに従った。
ありがたさより、情けなさのほうが勝っていた。
部屋に戻って、しこたま酒を飲んだ。
ビール、チューハイ、日本酒。手当たりしだい口に入れた。
何を飲んでいるのか、途中からよく分からなかった。
午前2時、携帯が鳴った。
画面には、見慣れた番号が光っていた。
彼女だった。
ワンコール、ツーコール。
親指が勝手に震えた。
出れば、何かが決定的に変わってしまう気がした。
怖かった。
僕は通話ボタンではなく、切断ボタンを押した。
プツッ。
部屋の中が、さっきまでより急に静かになった気がした。
さっきまでの酔いが、変な方向にまわりはじめる。
深夜にもかかわらず、彼女が置いていったCD、
彼女のお気に入りの曲を大音量で流した。
自分でもよく分からない怒りが、胸の中でぐるぐるし始めた。
彼女に対してなのか、妹さんに対してなのか、
父親たちに対してなのか、自分自身に対してなのか。
もう、誰に向けたらいい怒りなのか分からなかった。
僕は、残っていたウォッカの瓶をつかんだ。
ラッパ飲みで喉に流し込む。
胃が焼けるように熱くなって、目の奥がじんとした。
気づいたら、車に乗っていた。
こんな状態で運転しちゃいけないなんてことは、
頭では分かっていた。
でも、そのときの僕には、どうでもよくなっていた。
ハンドルを握って向かった先は、自分が働いている店だった。
深夜の街は、思ったより静かだった。
店の前のシャッターは半分閉まりかけていて、
中では男性スタッフが後片付けをしていた。
「おつかれさまですー」
と声をかけられた気もする。
でも、その声は耳の手前で弾かれた。
「うぉぉぉぉぉーーーー!!」
気づいたら、店の壁を両手で殴っていた。
貼ってあったポスターを引きはがし、
カーテンを力任せに引きちぎった。
何に対して怒っているのか、自分でも分からなかった。
ただ、どこかにぶつけないと、心の中が破裂しそうだった。
「おい、やめろって! なにしょん!」
誰かが後ろから羽交い締めにしてきた。
その声も、腕の力も、全部まとめて振りほどきたかった。
店長が慌てて電話をかけるのが見えた。
ああ、警察を呼ばれたな、と思った。
向けようのない怒りだった。
彼女にぶつけるわけにもいかない。
妹さんにも、父にも、世界にも。
いちばん殴りたかったのは、自分自身だった。
最後の言葉
店の壁を殴り、カーテンを引きちぎったあと、僕は警察に連れて行かれた。
事情を聞かれ、店長にも頭を下げて、
結局は一ヶ月分の給料をそのまま弁償にあてることで示談になった。
鉄格子のない、味気ない取調室の椅子に座りながら、
「何やってるんだろうな、俺」と何度も思った。
怒りの行き先を間違えたことくらい、自分がいちばん分かっていた。
翌日、署を出た足で、僕は彼女の部屋へ向かった。
どうしても、あの電話のことを謝りたかった。
出なかったことを。
あのとき切ってしまったことを。
インターホンを押すと、少し間をおいてからドアが開いた。
「……どしたん?」
開いたドアの向こうで、彼女がきょとんとした顔をしていた。
僕の頬のアザと、腫れた拳を見て、すぐに表情が変わった。
「その怪我、どしたん?」
「ちょっと、な。理不尽なこと言われて腹立って、やらかした」
本当のことは言えなかった。
言ったところで、たぶん笑い話にはならない。
彼女は何も言わずに部屋に上がり、財布を取り出した。
テーブルの上に、一万円札を一枚、静かに置いた。
「お金がいるんでしょ」
その言い方が、妙に冷静だった。
「いや、違う。金が欲しいわけじゃない。
昨日の電話、出んかったことを謝りたかっただけで……」
言い訳みたいな言葉が、口からだらだら出てくる。
自分でも情けないと思いながら、それでも止まらなかった。
彼女は僕の顔をしばらく見てから、ゆっくりと口を開いた。
「同情はせんよ」
一拍おいて、続けた。
「帰って。もう魅力も何も感じん」
それが、最後の言葉だった。
ドアが閉まる音が、やけに大きく響いた。
廊下にひとり残されて、手の中で一万円札をぐしゃぐしゃに握りつぶした。
返すタイミングを逃して、そのままポケットに突っ込んだ自分も、嫌いだった。
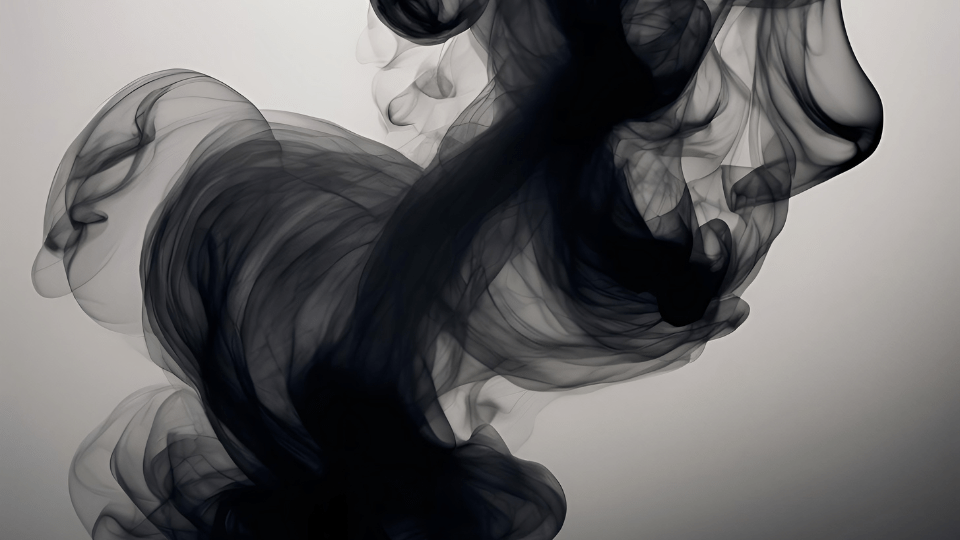
あれから、彼女とは一度も会っていない。
連絡先も、とっくに分からなくなった。
今、彼女も四十代になっているはずだ。
きっと、どこかで普通に笑っていると思う。
妹さんと助け合いながら。
そうであってほしいと、勝手に思っている。
僕があのとき守れなかったものも、
向けようのない怒りで壊してしまったものも、
全部ひっくるめて、彼女の人生のほんの一部分であればいい。
夜の店での社内恋愛は厳禁だ。
それでも、あの時間がなかったら、
僕は「誰かのためにそこまで自分を削る」という生き方を、
あんなに近くで見ることはなかったと思う。
彼女はソープで働くことを選んだ。
僕は何も選べないまま、ただ怒って、ただ壊した。
その差が、今でも胸のどこかに刺さったままだ。

次の記事はコチラ👆👆👆
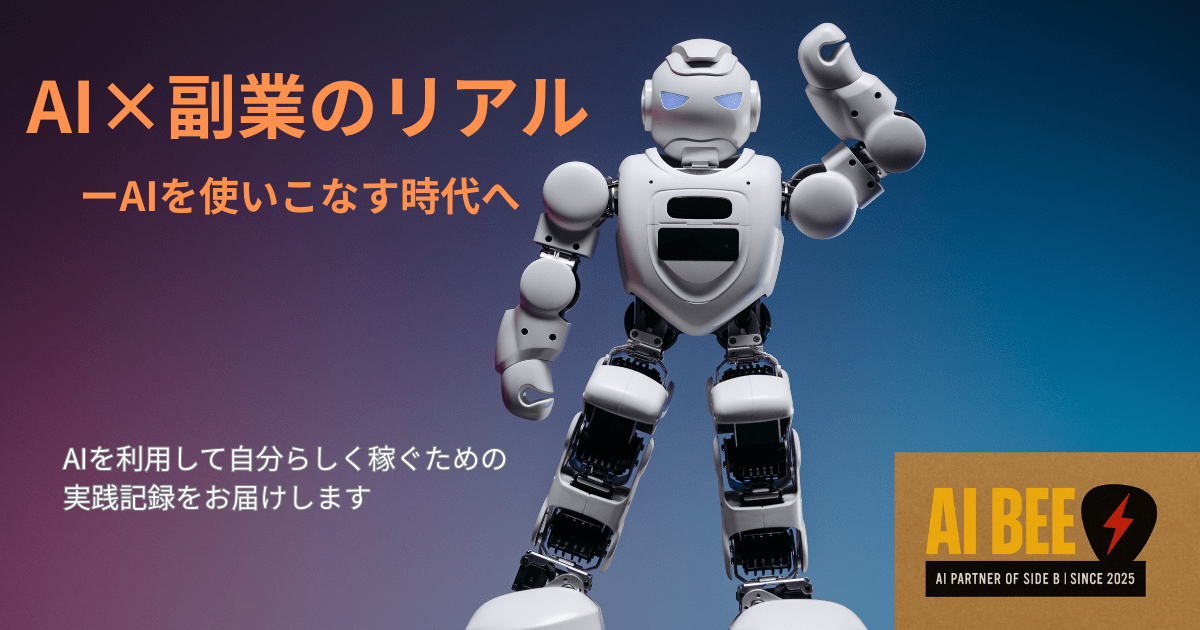
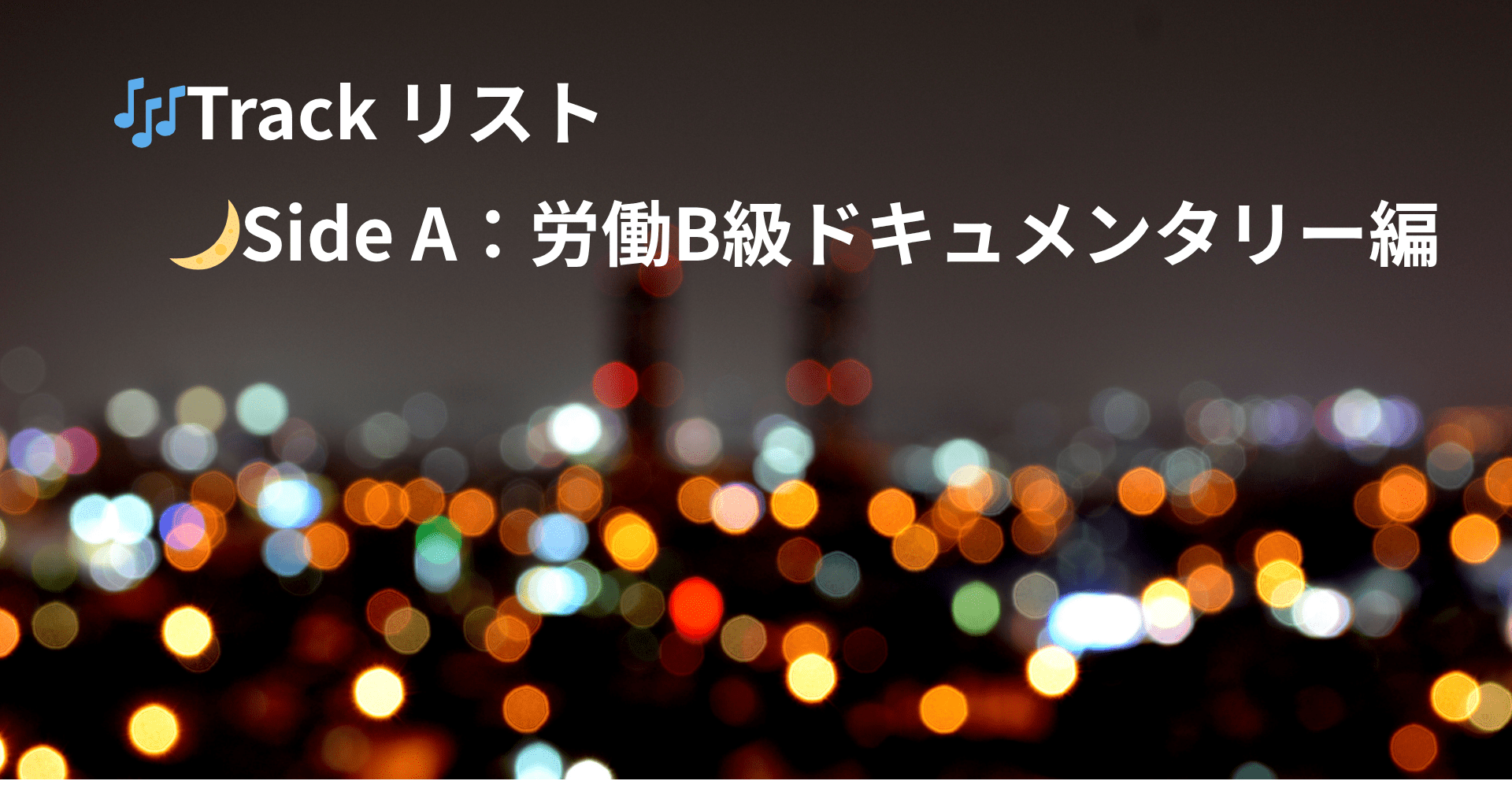


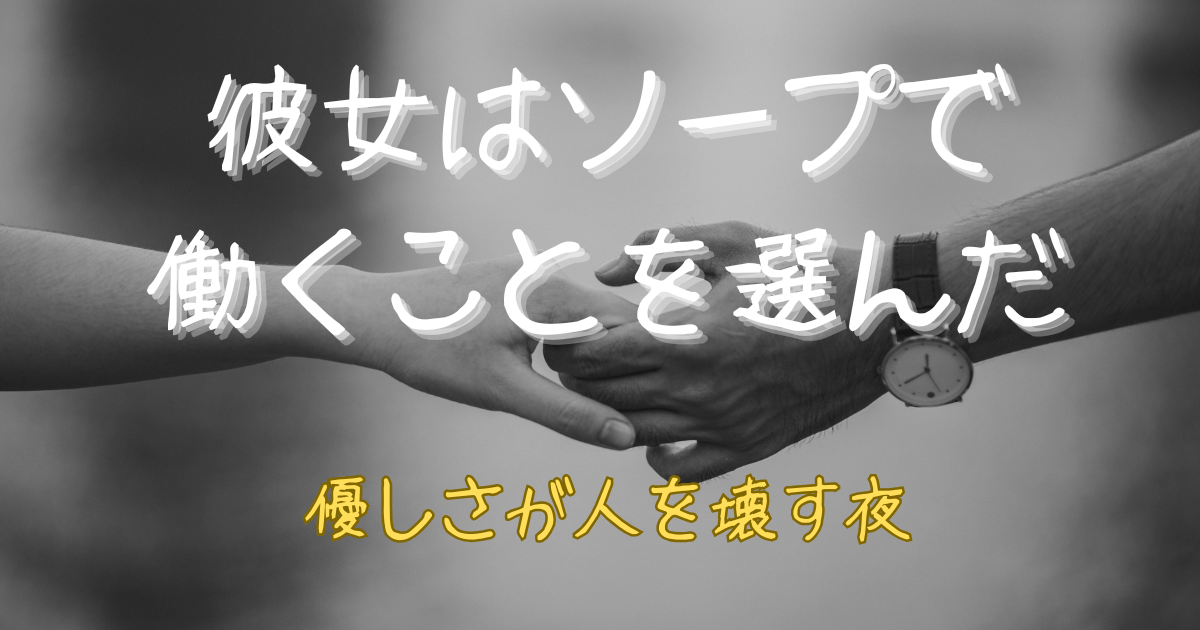

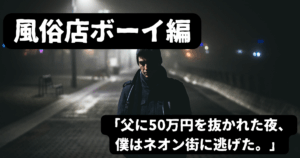


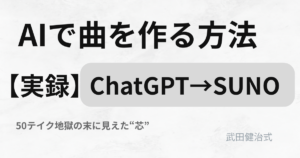

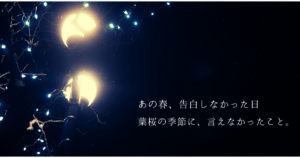
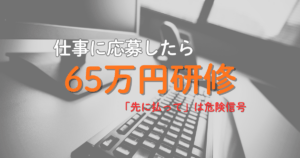



コメント